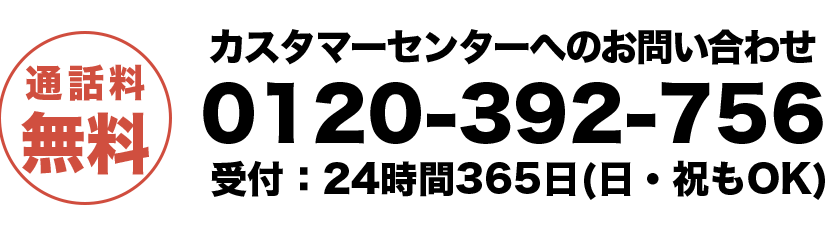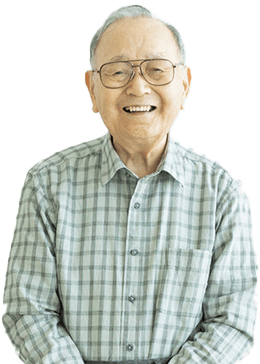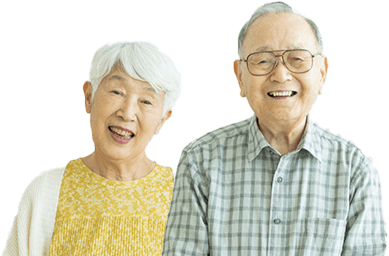2000人を看取った医師が「終末期の患者は自宅に帰る方がいい」と断言する理由
2023年4月18日2023年4月19日
2000人を看取った医師が「終末期の患者は自宅に帰る方がいい」と断言する理由
萬田緑平:「緩和ケア 萬田診療所」の院長
健康 ニュースな本 2023.3.23 3:25
2000人を看取った医師が「終末期の患者は自宅に帰る方がいい」と断言する理由

人はみな平等に“死”を迎えますが、最期の瞬間をどう迎えるかは人それぞれ。
病院や介護施設で終末ケアを受けて天寿をまっとうする人が多い昨今、終末期に自宅で過ごしたい患者をサポートする在宅緩和ケア医の萬田緑平氏は「人生の最終章には、『家で死ぬ』という選択もある」と話します。
本稿では、『家で死のう!――緩和ケア医による「死に方」の教科書』(三五館シンシャ)の一部を抜粋・編集しお送りします。
目次[ close ]
そもそも死は苦しいものじゃない
緩和ケアとは、重い病を抱えている患者さんやその家族の心身のさまざまな苦痛を予防したり、やわらげたりする医療のことです。一般的には病院の緩和ケア病棟で受けることができます。緩和ケアを専門とする医師のほとんどは病院の勤務医です。
一方、私は開業医として緩和ケアを行なっています。終末期に自宅で暮らしたい患者さんをサポートするので、「在宅緩和ケア医」と名乗っています。
病院での治療をやめて、自宅で生きることを選んだ患者さんの中には、すぐに亡くなってしまう方もいます。しかし、その最期は、病院で見られる絶望的な「死」とはまったく異なり、みなさん穏やかな表情で亡くなっていきます。私は病院医療と在宅緩和ケアの両方を見てきた立場として、こう断言します。
「終末期の患者さんは、病院での延命治療をやめて、自宅に戻ってすごしたほうが人間らしく生きられる」と。
病院の医師は、人間の死がこんなにも穏やかなものだとは知りません。
病院が当たり前に行なっている治療をやめて、上手に支援すれば、多くの人が苦痛から解放されて、最期のときまで穏やかに生き抜くことができるのです。
人は誰もが死にます。だんだん元気がなくなり、だんだん食事がとれなくなり、だんだん歩けなくなり、寝ている時間が長くなります。
そのうち水も飲まなくなり、トイレにも行かなくなります。そして、深い眠りに入って意識がなくなると、ついには呼吸が弱くなり、とうとう呼吸が止まります。それと同時に、心臓が止まる。これが、人が死ぬということです。
その人の病状や残された体力によって、この経過が1日でくる人もいれば、数年かけて訪れる人もいます。
基本的には、そこに悶え苦しむような体の苦痛はありません。
以前の私もそうでしたが、病院の医師はこのことを知りません。
病院には治療の末に亡くなる患者さんしかいないからです。
病院では死なないように懸命に治療した結果、患者さんは必ず亡くなっていきます。
だから、治療するほうも治療されるほうも、精神的にもつらい。穏やかな死とは、飛行機がゆっくりとソフトランディングしていくようなイメージです。
経年劣化によってエンジンや翼はボロボロになってしまったけれど(歳をとって体中病気だらけだけど)、無理して燃料を詰め込まず(無理して食事や水分をとらず)、機体が骨組みだけになっても(ガリガリに痩せても)、死という運命に抗わずに、ゆったりと自分のペースで飛び続け、いつのまにか着陸している。
そんなイメージです。低空飛行となってゆっくりと着陸すれば、死は決してつらくありません。
そして、このような穏やかな死を迎える場として、自宅ほどふさわしい場所はありません。
「良く生きて、良く死ぬ」そのための選択
人生の最終章には、「病院で治療する」という選択肢以外にも、治療をやめて「家で生き抜く」(それはつまり「家で死ぬ」)という選択肢があることを知ってほしいと思います。

医師や病院に言われるがままにつらい治療を継続して、「生かされた」状態のまま逝くのではなく、最期まで自分らしく「家で生き」「家で死ぬ」ために、私の「在宅緩和ケア」はあります。
私の診療所の大きな方針は「本人が好きなように」「本人が望むこと」をサポートすることです。本人の人生なのだから、本人に主導権を取り戻してもらうのです。
だから、体にいいことだからといって、本人が望まないことはさせません。つねに「本人の笑顔を引き出す」にはどうすればいいかをケアの中心にしています。
緩和ケアと聞くと、「死ぬ前の人が行くところ」と認識している人もいるでしょう。そのとおりです。
だから、「死にたくない」「死なせたくない」「死ぬはずがない」と思っている患者や家族は、私のもとにやってきません。病院で治療を続けても、人は死ぬのです。
そして、多くの場合において、苦しみながら死んでいきます。どうせ死ぬのなら、より苦しみのない方法がいい、そして最期まで自分らしく生きたい、そう考えられる人や家族が治療をやめて在宅緩和ケアを選びます。
「病院で治療をやめる」ということは、「死を認める」ということかもしれません。
「死を認める」ことができるかは、当事者になってみなければわからないことでしょう。
私も、いざ患者の立場になったとき、どう感じるのかはわかりません。
在宅緩和ケアを選択し、穏やかに亡くなっていった人はみなさん、ある程度「死を認めていた」ように思えます。
「自宅で死にたい」を尊重したある患者の看取り
「人間的な死」を迎えるためのお手伝いはAIには代理できない。看取りの経験を重ねるにつれ、その思いを強くします。
85歳の安藤ウメさんは一人暮らしをしていました。私のもとに娘さんとやってきたときはすでに前の病院で余命1カ月と宣告されていました。
娘さんは「自宅で死にたい」という母親の気持ちを受け止め、病院に入院させず、私に母親の看取りを託すことを選びました。
娘さんは茨城で忙しい毎日を送っており、群馬の実家に戻れるのは月に一度あるかないかです。
こういった場合、多くの人が病院に入院させることを選びますが、彼女はあくまで「本人の意思」を尊重したのです。
ウメさんは食べられたり食べられなかったり、歩けたり歩けなかったりを繰り返しているうちに、いつのまにか半年の月日が流れていました。
「ぽっくり逝きたい。眠るように逝きたい」と言うウメさんに、私たちは「絶対に苦しい思いはさせないから」と約束しました。
終末期のがん患者さんが耐えがたい痛みや呼吸困難の苦しみに襲われたとき、薬を使って意図的に意識を落とすことで苦痛を緩和する医療行為を「セデーション」といいます。
私はウメさんと娘さんにセデーションについてすでに説明していました。
そしてついにウメさんは呼吸が苦しい状態になっていきました。
「先生、楽にしてくれる約束だったよね。昨夜は大ごとで、こんなんじゃ死んじゃったほうがいいなって。約束の薬、頼むよ。いいんだよ、もう目覚めなくても」
「娘さんに連絡するから、娘さんがいいって言ってくれたらね」
「大丈夫だよ。私がいいって言えば大丈夫だよ」 「残された人のことも考えてあげてください。
娘さんがかわいそうでしょ」 しかし、娘さんとは電話がつながりません。ウメさんからは「至急だよ」と急かされます。
数時間経って、ようやく娘さんと連絡が取れ、確認のうえ、薬を皮下注射。しばらくすると、ウメさんの意識はもうないように見えました。ところが、突然、「安心したよ、先生」と口が動きました。
「安心して天国に行ってください。行ってらっしゃい」私はそう応じました。 ウメさんは私の手を握り続けていました。しばらくして、また口が動きます。
「先生、また会おうね」 「いつかまた、会いましょう」 1分ぐらいしてから、
「来月ね!」 「来月じゃ困るよ……30年後にしてね」
「わかった」 これがウメさんと私の最後の会話となりました。
半年以上のつきあいのウメさんが亡くなり、こうした別れは日常茶飯事の私もうるっと来ました。一方、担当の看護師は晴れ晴れした表情をしています。彼女はすでにお別れのあいさつをウメさんとしていて、そのときたくさん泣いたそうです。事前にしっかりお別れのあいさつをしておくことは、家族だけではなく私たちスタッフにも大切なことだとあらためて感じました。
一人暮らしを好み、最後まで自宅で生きたいと思っているお年寄りは大勢います。施設に入るのを拒否し、子どもたちに「一緒に暮らそう」と言われても、好んで一人暮らしを続けている人も少なくありません。
高齢で生活スタイルを変えるのは、死ぬよりも怖いことなのです。
ウメさんのようなお年寄りの望みを叶えるためにも、もっと在宅緩和ケアが広がる必要があると思います。
数字やデータに表れない「人間の心」に寄り添うからこそ、私の在宅緩和ケアはAIで行なうことは不可能なのです。